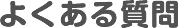トップページ >
よくあるご質問
相続
- 父が10日前に亡くなりました。まず、やるべきことは何ですか?
- 人が亡くなると、その人の財産は、その相続人(配偶者、子供等)に引き継がれます。葬儀等が終わって、しばらく時間をおいて、冷静になって手続きに入りましょう。
① 遺言書があるかを確認します。
自筆証書遺言~開封せずに、家庭裁判所に「検認」の申立てをし、遺言書を保全しておきます。 公正証書遺言~遺言の内容を実現するには、遺言執行者の選任を家庭裁判所に申立てる必要がある場合があります。 遺言書が無い~相続人が全員で協議して、遺産の帰属を決定することになります。
② 相続財産として何があるかを調査します。
不動産、預貯金、現金、株式・有価証券、生命保険金、貴金属、自動車等について。調査の結果、マイナスの遺産(債務、借金等)が多いようであれば、相続放棄を検討することになります。
相続放棄をすれば、その相続人は初めから相続人ではなかったことになりますが、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申立てる必要があります。
③ 相続人の調査をします。
亡くなった方の戸籍(出生から亡くなるまで)を取り寄せて、相続人が誰であるかを確定します。認知した子、養子縁組をした子が出てくるかもしれません。
- 遺産分割の協議が相続人の中でまとまりません。方法はありますか?
- 話合いがまとまらないときは、相続人の一人が他の相続人の全員を相手方として、相手方所在地の家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。調停は裁判所の調停委員が間に入って話合いを進める手続きです。 調停でも話合いがまとまらない場合は、裁判所が審判を下し、遺産分割の方法を決めます。法定相続分が目安となります。不服があれば、即時抗告で更に争うことになります。
遺言
- 封印された遺言書があったのですが、開けて見てしまってもよいのでしょうか?
- 封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人又はその代理人の立会いがなければこれを開封することは出来ません(民法1004条3項)。尚、公正証書遺言以外の方式による遺言については、まず家庭裁判所において「検認」を受けなくてはなりません。
- 亡くなった主人の遺言書が見つかりました。全財産を長男に相続させるという内容でした。私(妻)と次男は納得できません。この遺言書の内容に従わなければならないのでしょうか?
- 被相続人(亡くなった人)は、その財産を自由に処分することができますが、この自由を無制限に認めてしまうと、相続人に多大の犠牲を強いる結果となるため、法律は遺留分の制度を認めています。(民1028条)
遺留分とは、被相続人が遺言によっても処分することができない相続分の事です。 遺留分の範囲は、被相続人の直系尊属のみが相続人の場合は相続財産の3分の1、その他は2分の1です。但し、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分を侵害する遺言であってもただちに無効となるものではなく、相続人が遺留分減殺権を行使した時に取戻す権利が発生します。(注:1年で消滅時効)
その他
- 相続した不動産を近いうち売却する予定ですが、それでも相続登記は必要ですか?
- 必要です。不動産の売却前に相続が発生した場合には、亡くなられた方から相続人へ権利が承継されたことを登記しなくてはならず、相続登記を省略して亡くなられた方から直接売買契約の買主名義に移転登記をすることは出来ません。
- 再度の遺産分割協議による相続登記のやり直しは可能ですか?
- 相続人全員が、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割の協議をすることは可能ですので、それによって相続登記のやり直しをすることも出来ます。但し税務上の問題として、遺産分割のやり直しは贈与税等の課税対象となってしまう恐れがありますので注意が必要です。


![06-6949-8672 [受付時間]平日:9:00~21:00](img/common/contactText.png)